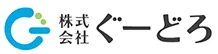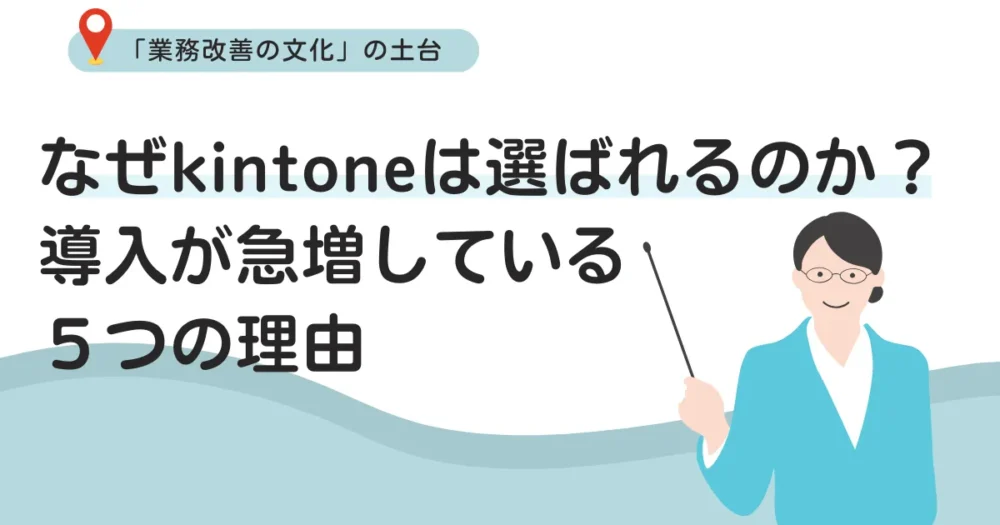2025年07月13日
なぜkintoneは選ばれるのか?導入が急増している5つの理由
「Excelの関数やマクロが複雑化し、作った本人しか直せない…」
「メールでの報告は、過去の経緯を遡るのが大変で、Cc漏れで情報格差が生まれてしまう…」
「DXを進めたいが、IT専門の人材も開発予算も限られている…」
もし、あなたの会社がこのような課題を抱えているなら、それは決して珍しいことではありません。多くの企業、特にリソースが限られる中小企業にとって、これらは日々の業務に潜む共通の悩みと言えるでしょう。
こうした状況を改善する有効な手段の一つとして、今、多くの企業から注目を集めているのが、サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone(キントーン)」です。
「名前は聞いたことがあるけれど、グループウェアと何が違うのだろう?」
「なぜ、様々な業種・規模の企業で導入が進んでいるのだろう?」
と興味を持つ方が増えています。 (導入社数:35,000社以上)
本記事では、kintoneがビジネスの現場で選ばれる「5つの理由」を、具体的な活用シーンを交えながら、分かりやすく解説していきます。
【理由1】プログラミングの知識がなくても、自社に合ったシステムを作れる
kintoneが支持される大きな理由の一つに、その「導入の手軽さ」があります。
●専門知識がなくても業務アプリを作成できる
従来のシステム開発では、専門家による要件定義やプログラミングに、多くの費用と長い期間が必要でした。
一方、kintoneは「ノーコード/ローコード」という、プログラムを書かなくてもシステムを構築できる考え方で設計されています。パワーポイントでスライドを作るような感覚で、必要な項目(文字列、数値、日付、添付ファイルなど)を画面上にドラッグ&ドロップで配置するだけで、自社の業務に合わせたデータベース(kintoneでは「アプリ」と呼びます)が完成します。
例えば、これまでExcelで別々に管理されていた以下のような情報も、kintoneで手軽にアプリ化できます。
・営業部: 顧客リスト、案件管理、商談日報
・管理部: 備品管理、契約書管理、問い合わせ管理、採用進捗管理
・経理部: 経費申請、交通費精算
・全社共通: タスク管理、社内Q&A、プロジェクト進捗管理
Excelで起こりがちな「担当者による表記ゆれ」や「計算式の誤入力」といった問題も、入力ルールの設定や変更履歴の自動保存機能で防ぎやすくなり、誰もが安心して使えるデータベースを構築できます。
●「スモールスタート」で着実に導入できる
「いきなり全社で新しいシステムを導入するのはハードルが高い」と感じる方も多いでしょう。kintoneは月額制で、少人数から利用を始められます。
例えば、「まずは営業部の数名で日報システムから試してみよう」という「スモールスタート」が可能です。そこで効果を実感してから、「次は案件管理システムも作ってみよう」「管理部にも展開して備品管理に活用しよう」といった形で、段階的に適用範囲を広げていけます。初期投資を抑え、リスクを回避しながら、社内のDXを推進できる点も魅力です。
【理由2】業務の変化に合わせて、現場で改善を続けられる
kintoneの特長は、一度作って終わりではなく、ビジネスの変化に合わせてシステムを「育てていける」点にあります。
●現場主導で回す、改善のサイクル
ビジネス環境は常に変化するものです。新しいサービス、市場のニーズ、法改正など、昨日までのやり方が通用しなくなることも少なくありません。
従来のシステムでは、こうした変化のたびにシステム会社へ改修を依頼し、追加の費用と時間が必要でした。しかしkintoneなら、業務を一番よく知る現場の担当者が、その場で「もっとこうしたい」という気づきをシステムの改善に活かせます。
「入力項目が足りないから追加しよう」
「選択肢の順番を変えた方が分かりやすい」
「よく使う絞り込み条件を保存しておこう」
こうした小さな改善の積み重ねが、業務効率の向上につながります。IT部門に過度に依存することなく、現場が主体となって業務改善を進める。この「現場主導の改善サイクル」が、変化に対応しやすい組織づくりに貢献します。
【理由3】プラグインで、必要な機能を柔軟に「後付け」できる
kintoneの基本機能をOSに例えるなら、「プラグイン」は専門的な機能を追加するアプリケーションソフトのような存在です。標準機能だけでは実現が難しいことも、国内外のパートナー企業が開発・提供する多様なプラグインを導入することで、自社のニーズに合わせて機能を拡張できます。
例えば、以下のような機能も、プラグインを使って実現可能です。
・帳票出力: kintoneのデータを引用し、ワンクリックで見積書や請求書をPDF出力
・Webフォーム連携: ホームページのお問い合わせフォームと連携し、入力内容を直接kintoneに登録
・電子契約連携: kintone上で管理する契約情報と、電子契約サービスを連携
・LINE連携: 顧客とのLINEでのやり取りをkintoneに記録・管理
そして、特に「場に関する情報を扱う業務において、kintoneの活用範囲を広げるのが地図連携プラグインです。
●「Kマッププラグイン」で地図情報を業務に活用
営業、店舗開発、保守メンテナンス、配送計画など、多くの業務は地図と密接に関わっています。しかし、kintoneに登録された住所録は、ただの文字情報のリストになりがちです。
「リスト上の住所を見ても、どのエリアに顧客が集中しているか直感的に分かりにくい…」
「現場ごとの作業進捗を確認するのに、地図とリストを照らし合わせる手間がかかる…」
「新規出店を検討しているが、商圏分析に使えるデータがほしい…」
こうした場合に役立つのが、『Kマッププラグイン』です。kintoneに登録された顧客情報や住所データをもとに、Googleマップ上にピンを立てて可視化したり、データの密度を色で表現するヒートマップを作成したりできます。これにより、勘や経験に頼りがちだったエリア戦略をデータに基づいて立案するなど、営業活動や店舗開発の精度向上をサポートします。
ご興味のある方は、ぜひこちらの製品ページもご覧ください。
→ [Kマッププラグイン製品紹介ページへ]
【理由4】社内の情報を一元化し、「探す時間」を削減する
情報は、活用されて初めて資産となります。kintoneは、社内に点在しがちな情報を集約し、活用するための「ハブ」として機能します。
●「あの情報、どこだっけ?」という状況をなくす
あなたの会社では、重要な情報が個人のPC内のExcelファイルや、過去のメール、共有フォルダの奥深くに眠っていませんか?このような情報の「サイロ化」は、業務の属人化を招き、情報を探すだけで多くの時間を費やす原因となります。
kintoneは、これらの情報を一つの場所に集約します。さらに、kintoneの優れた点は、集約した情報をアプリ間で「連携」させられる点にあります。例えば、「顧客マスタ」アプリに登録した会社情報を、「案件管理」アプリや「問い合わせ管理」アプリから呼び出す(ルックアップ機能)ことで、入力の手間を省き、情報の正確性を保つことができます。
この「情報のハブ」としての機能が、会社全体の業務効率化の基盤となるのです。
●全文検索とデータ集計で、見たい情報にすぐアクセス
kintoneに蓄積された情報は、強力な全文検索機能により、アプリを横断して簡単に見つけ出すことができます。ファイル名だけでなく、添付されたWordやExcel、PDFファイルの中身まで検索対象となるため、「あの会議で使った資料」といった曖昧な記憶からでも、必要な情報にたどり着きやすくなります。
さらに、蓄積されたデータは、リアルタイムでグラフ化することも可能です。「今月の売上状況はどうか」「問い合わせが多い製品は何か」といった、状況把握に必要な情報をいつでも最新の状態で可視化し、迅速な判断を支援します。
【理由5】スマートフォン活用で、場所を選ばない働き方を実現
kintoneは、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットにも最適化されています。このマルチデバイス対応が、場所に縛られにくい柔軟な働き方を後押しします。
・外出先の営業担当者が、商談直後にスマートフォンの音声入力で日報を作成する。
・建設現場の監督が、タブレットで撮影した進捗写真をリアルタイムで本部に共有する。
・店舗の担当者が、各店の状況をチェックリストで報告し、マネージャーが移動中に確認する。
こうした活用が可能になることで、報告や承認のためだけにオフィスに戻るといった非効率な時間を削減し、社員一人ひとりの生産性向上をサポートします。また、自分宛ての通知(タスクの割り当て、申請の承認など)をスマートフォンで受け取れるため、対応漏れや確認の遅れを防ぎやすくなります。
まとめ:kintoneは、業務改善の文化を育む土台に
今回は、kintoneの導入が広がっている5つの理由について解説しました。
1.【柔軟性】 プログラミングの知識がなくても、自社に合ったシステムを作れる
2.【成長性】 現場の声を反映させながら、継続的にシステムを改善できる
3.【拡張性】 プラグインで、帳票や地図連携など必要な機能を追加できる
4.【情報活用】 社内の情報を一元化し、検索機能で「探す時間」を削減できる
5.【機動性】 スマートフォン対応で、いつでもどこでも仕事ができる環境を整えられる
これら5つの理由はそれぞれが独立しているのではなく、互いに連携することでkintoneの価値を高めています。
kintoneは単なるITツールというだけでなく、社員一人ひとりが「もっと良くするにはどうすればいいか」を考え、実践する「業務改善の文化」を育むための土台となり得ます。
本ブログでは、今後も建設業や人材業、営業部門など、より具体的な業種・業務でのkintone活用法についても解説しています。自社の業務にどう活かせるか、ぜひヒントを探してみてください。
そして、地図や位置情報を活用した業務効率化に少しでもご興味をお持ちいただけましたら、kintoneをさらに便利にする『Kマッププラグイン』の詳細を、ぜひ一度ご覧ください。
参考情報
・Kマッププラグイン製品紹介ビデオ